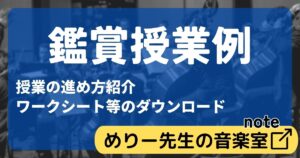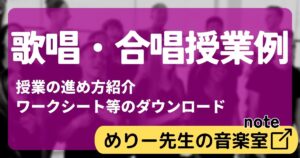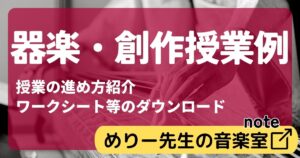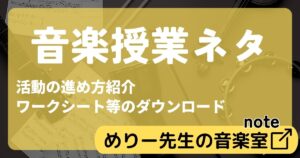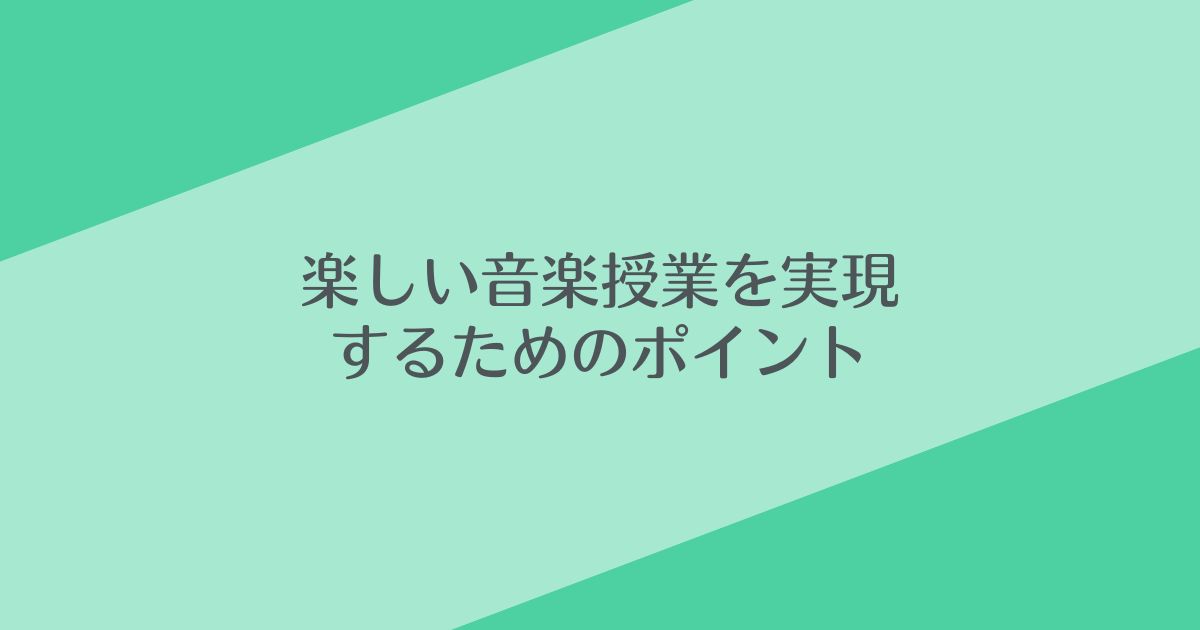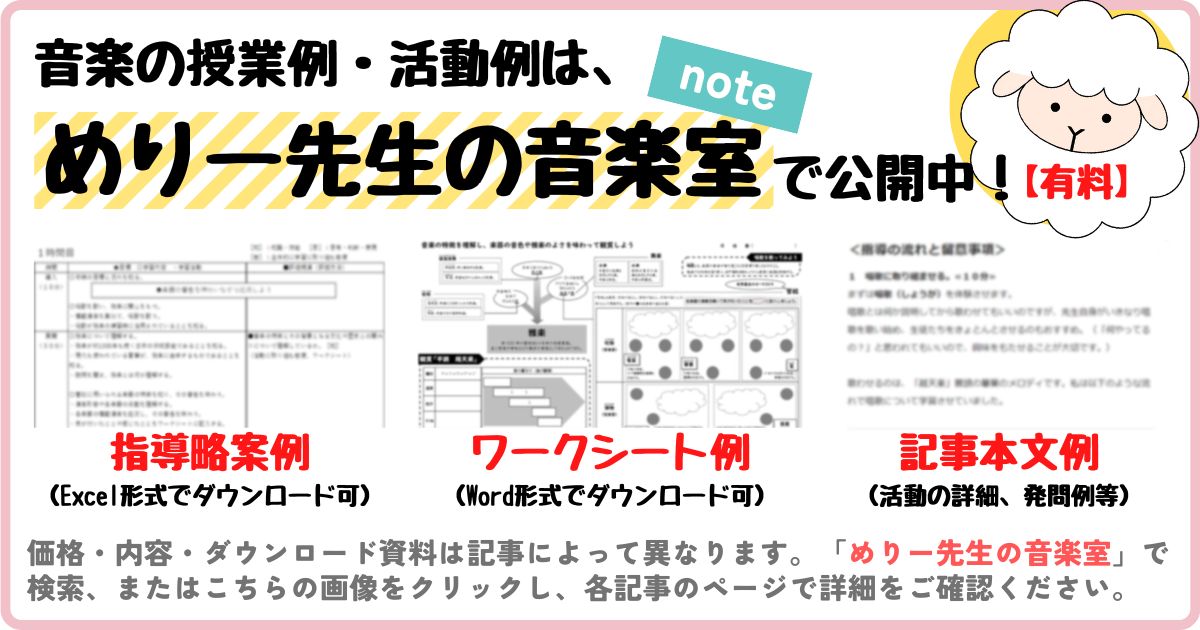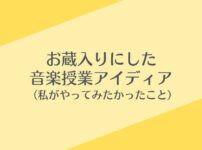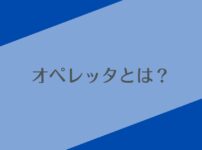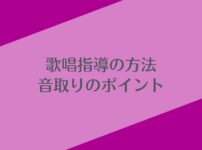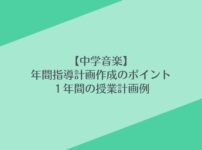音楽の先生方、音楽の授業がつまらない。楽しい音楽授業はどうやったらできるの?とお悩みではないですか?
私も教員時代、ずっとこの難問に頭を抱えていました。
ですが、正直これは永久に悩み続けなければならないことなのかなと思います。
というのも、時代や社会背景、地域や学校の状況、生徒が変われば、その都度「楽しい」の感覚は変わるからです。
というわけで、この記事では、音楽の先生である以上、追求し続けなければならない、楽しい音楽授業の実践について、私が意識していたことをまとめてみます。
※今回の記事は音楽授業全般に関する内容ですので、もし鑑賞授業にお悩みであれば、こちらの記事も合わせてご覧ください。
-

鑑賞授業のコツは?元中学校音楽教員が意識していた7つのこと
続きを見る

目次
楽しい音楽の授業とは?
生徒の「楽しい」と先生の「楽しい」は違う!?
「○○先生は雑談が面白いから授業が楽しい。」のように、こちらが意図しない「楽しさ」を生徒が感じている状態を素通りしていませんか?
もちろん、先生個人の魅力を生かした授業づくりは大切なことですし、雑談や、ゆとりのない授業は、正直面白くありません。
ですが、それが「楽しさ」の一番の理由になってしまうのは、本来学校教育が意図することとかけ離れているような気がします。
楽しい授業とは、教科特有の「楽しさ」が感じられる授業であり、それを実現するために先生個人の魅力を生かすというのが理想的な形だと私は考えます。
音楽の「楽しさ」は先生自身が一番よく分かっている!
この記事をご覧の方は、音楽に対して何らかのプラスの感情を持っているからこそ、音楽を続け、先生という仕事をしている(目指している)のだと思います。
では、皆さんが音楽を「楽しい」と思うのはどのような瞬間ですか?
おそらく、その答えが音楽の授業をより楽しくするポイントにつながるはずです。
例えば、私は、
・美しい音楽を聴いたとき
・仲間と一緒に歌っているとき
・上手に演奏できたとき
・今まで知らなかった音楽と出会ったとき
に特に音楽の「楽しさ」を感じます。
だから、私の授業では、
・なるべく本物に近い演奏を聴かせる
・たくさん歌って演奏する時間を確保する
・技能的なアドバイスを具体的に行う
・様々な音楽に触れる機会を作る
ようにしていました。
このように、自分の思う「楽しさ」を生徒が感じるためにはどうすればよいのかを考えてみると、楽しい音楽授業を行うヒントが見つかるのではないでしょうか。
楽しい音楽授業のために意識していたポイント
さて、ここからはより具体的な話として、私が楽しい音楽授業を実現するために意識していたことをいくつかご紹介します。
・音楽に触れる時間をたくさん作る
皆さんは1時間の授業のうち、どのくらいの時間、生徒が音楽に触れているか計ったことはありますか?
私は初任教員時代、抜き打ちで授業を見に来た指導教員に計測されたことがあります。
その時は確か「魔王」の鑑賞授業だったのですが、授業の冒頭(3分)と授業の終わり(3分)の計6分しか音楽に触れていないことが分かり、愕然としました。
他の44分は何をしていたのかというと、曲に関する説明と感想記入です。
音楽の授業なのに、音楽に触れる時間が10分もないなんてあり得ないですよね。(授業がつまらないと思われても当然です。)

・テンポよく授業を進める
どの教科においても、授業のテンポ感は大切です。
速すぎると生徒はついてこられないし、遅すぎれば授業全体が間延びしてつまらなく感じてしまいます。
程よいテンポ感で、生徒がスムーズに学習できるよう、念入りな準備と事前のシミュレーションが必要です。
・教材の良さを見付ける
音楽の先生だって人間なので、得手不得手がありますし、正直好きな音楽とそうでない音楽だってありますよね。
ですが、授業で扱うにからには、個人的な感情は抜きにして、生徒にその音楽の良さが伝わるよう工夫する必要があります。
どんなに興味のない音楽でも、教材研究の際にはそれぞれの良さや美しさを見出すことが大切だと思います。
・自分の価値観を押し付けない
稀に「この部分はこういうイメージだから、こんな風に歌って」というように、自分の考えを前面に押し出している先生を見かけます。
人によって感じ方が異なるという点が音楽の良さのひとつでもあるので、先生の価値観を押し付けるような授業にならないよう、気を付けるべきだと思います。
・声を荒げない
全校合唱指導の際、「もっと口を開けろ」「大きな声を出せ」と怒鳴り声をあげる先生に遭遇したことはありませんか?
なんだか無理やり「歌わせている」感じがして、私はあの指導の仕方がすごく苦手でした。
だって、怒鳴られながら歌うなんてちっとも楽しくないし、何なら怒られると余計に歌いたくなくなりませんか?
音楽ほど、人の感情とつながっている教科はないと思うので、なるべくなら楽しい気持ちで音楽の授業を受けてほしいです。
ゆえに、危険行為や生徒の生命にかかわるようなアクシデント以外では決して声を荒げないよう、注意の仕方も工夫するようにしていました。
・身近なものや音楽と結びつける
音楽の授業がつまらなく感じる原因の一つに、クラシック音楽や合唱曲に対する苦手意識が挙げられます。
おそらく、教科書に載っている音楽が、普段自分たちが聴いている音楽とかけ離れた存在だと感じている生徒は多いでしょう。
そのような場合は、授業で扱う教材と流行りの曲との共通点を示すなど、身近な音楽と結び付けた授業を行うと効果的です。

・様々なジャンルの音楽を扱う
世界には様々な音楽がありますが、私たちが普段耳にする音楽は、そのうちのほんの一握りです。
ですが、いつもとは違う音楽を聴いたことで生徒自身の将来や見方・考え方が変わるかもしれません。
そんな音楽の力を信じて、私は5分間ミュージックという常時活動(詳しくはこちら)を通して様々なジャンルの音楽を生徒に聴かせていました。
・遊びやゲームの要素を取り入れる
教科書に沿って授業を進めるのはとても大切なことですが、時には遊びやゲームの要素を取り入れた方が、音楽の授業に対する印象は良くなります。
参考までに、おすすめの授業ネタをいくつかご紹介します。
上記のようにがっつりゲームを取り入れなくても、
・「交響曲第5番」に出てくる動機の数を数えよう
・(ピアノの鍵盤を1音叩いて)音が消えたら手を静かに下げよう
など、普段の授業の中に遊びの要素を取り入れることも出来ます。
・自分も生徒と一緒に楽しむ
結局のところ、一番大切なのは、先生自身が生徒と一緒に音楽を楽しむことです。
仏頂面で睨みを利かせれば、当然緊張感のある授業を行うことができますが、それ以上に生徒が萎縮してしまい、音楽を楽しむことはできません。
先生だけが楽しんでいるのは残念ですが、生徒の気分を高めるために、先生が授業を盛り上げようとすることは大切だと思います。
まとめ
さて、この記事では楽しい音楽授業を行うために意識していたポイントをご紹介しました。
少しでもお役に立てていれば幸いです。
続きを見る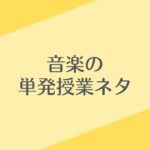
準備しておくと安心!音楽の単発授業ネタまとめ
\各教材の進め方や活動例はこちら/