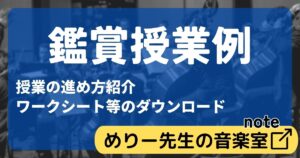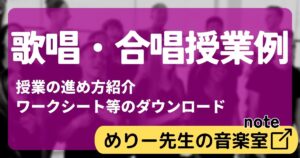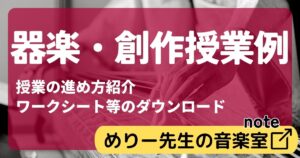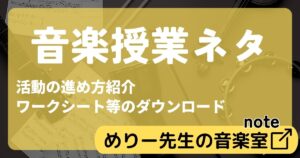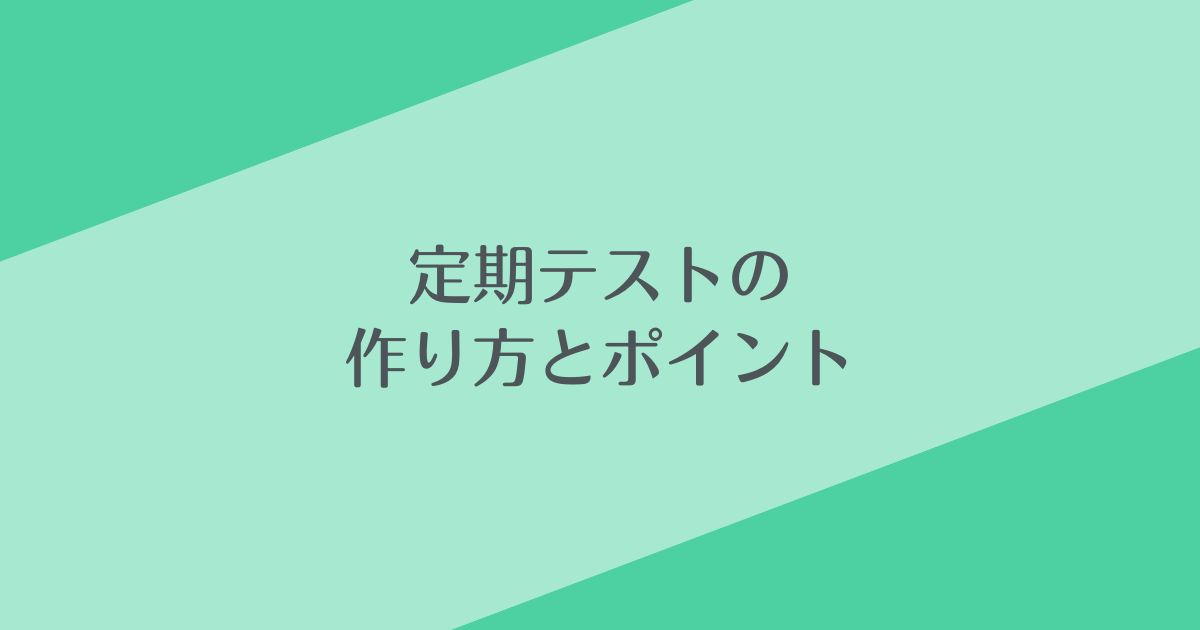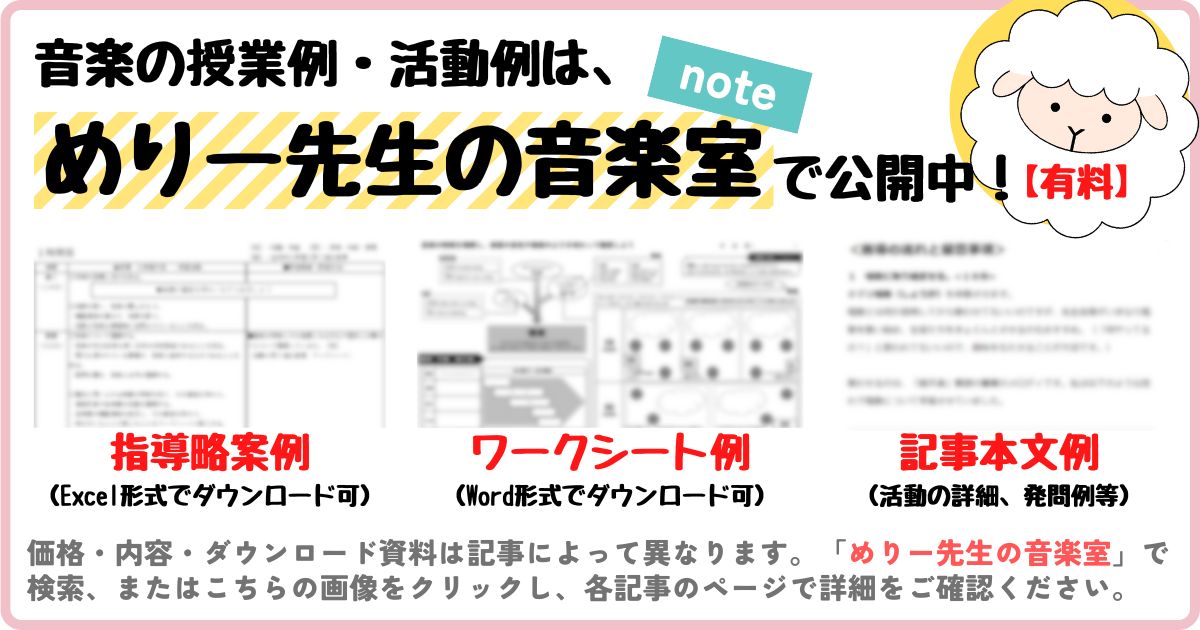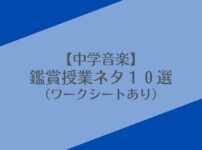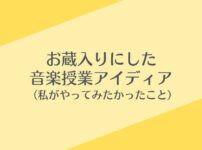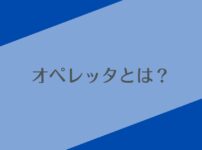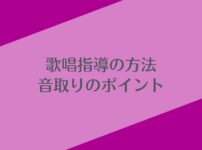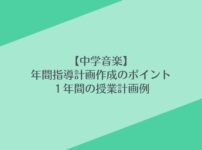初めてのテスト作りを控えている先生の中には、「テストってどうやって作るの?」「どのような問題を出せばいいの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では、過去に中学校音楽教員として勤務していた私の経験を基に、定期テストの作り方とポイントを簡単にご紹介します。
地域や校種、日頃の授業内容、生徒の実態等によって、テスト内容も大きく異なりますが、少しでも参考になれば幸いです。
目次
定期テストの作り方とポイント
1.目的を明確にする
学校によっては、「どの教科も筆記テストを行うのが当たり前」のような空気があるかもしれません。
ですが、なんとなく「全教科が行っているから」という理由でテストを実施するのは少し違うような気がします。
定期テストを作成する前に、いま一度、
・なぜ筆記テストを実施するのか
・テストでどのような力を評価したいのか
の2点について考えることで、出題方法や難易度がブレることなく、テストを作成できると思います。
2.解答時間と満点を決める
テストの実施時間と何点満点にするかを教科担当が決める場合もあります。
私が勤めていた学校では、ほとんどの教科が解答時間50分の100点満点でしたが、中には、解答時間30分で50点満点という教科もありました。
ただ、実施時間が短いと授業時数にカウントできない場合があるので、その辺りは教務主任や管理職にご確認いただくのが確実かと思います。
3.テスト範囲を決める
定期テスト実施日の1~2か月前くらいになったら、テスト範囲を決めます。
このとき、テスト直前に授業が終わる予定の題材は、範囲には含めないのがベターです。
早くからテスト対策をしている生徒はその部分の勉強ができなくて困りますし、万が一、授業が終わらないクラスがあった場合、直前に範囲を変えなくてはいけなくなるからです。
最低でもテストの1~2週間前には全クラスが授業を終えているところまでを範囲とするのが良いと思います。
4.問題を作成する
①大問は題材ごとに設定する
各題材の問題が散らばっていると混乱してしまう生徒もいるので、例えば、
2 「夏の思い出」
3 「フーガ ト短調」
4 「交響曲第5番ハ短調」
というように、1学期に学習した題材(教材)ごとに大問を作成すると分かりやすいと思います。

②日頃から問題をストックしておく
一度にテストを作るのは大変なので、授業準備や教材研究の際に、テストに出せそうな問題も作っておくのがおすすめです。
題材ごとに問題が用意できていれば、ストックしてある問題を組み合わせたり点数配分を決めたりするだけで良いので、テスト前に慌てる心配がありません。
③評価の観点を明確にする
評価の観点とは、【主体的に学習に取り組む態度】【思考・判断・表現】【知識・技能】のことです。
問題と観点が一致していないと、適切に評価を付けることができません。
例えば、【思考・判断・表現】の力が身に付いているかを評価したい場合に、
「rit.の読み方を答えなさい。」
という問題が適切かというと、そうでもないような気がします。
読み方が分かっているからと言って【思考・判断・表現】の力が身に付いているとは言えないからです。
もしも私がrit.に関する問題を出すなら、以下のようにrit.が付いている場合の演奏方法を問います。

これが必ずしも正解とは限らないのですが、少なくとも歌う時に注目すべき点や、rit.という記号の意味が分かっていなければ答えられない問題にはなっています。
上記のように、適切な出題方法や観点を意識してテストを作成することが、適切な評価につながると思います。
また、学校によっては、
・問題文に観点を明記する
・観点ごとに点数を出す
というような決まりがある場合もあるので、その辺りも漏れがないようにしておくと良いです。
5.解答用紙を作成する
解答用紙は、採点しやすいように作成するのがポイントです。
特に音楽などの実技教科の場合、全学年生徒の採点をすることが多いので、1~2日で何百人もの生徒の答案を採点することになります。
その後の集計や入力作業も莫大の量になるので、なるべく採点しやすい解答用紙を作っておくことをおすすめします。
また、隣り合った問題で点数が違うと集計しづらいので、「この段はすべて各1点」というように、可能な限り同じ点数の問題を集めておくのもコツのひとつです。
6.一度自分で解いてみる
テストが完成したら、必ず一度は自分で解いてみます。
問題文の誤植が見つかったり、解答枠の幅が狭かったり、満点にならなかったりと、必ずと言っていいほど一つは修正点があります。
また、その際には必ず時間を計るようにし、生徒が時間内にテストが終わるかもチェックすると良いです。
生徒は、自分が解き終わった時間の3倍はかかると考えると分かりやすいかと思います。
解答時間が30分のテストの場合、自分自身が10分で解き終われば、生徒にとってはちょうどよい問題数、難易度ということになります。

テスト作成時の注意点
・全クラスの足並みを揃える!
テストまでに全クラスの授業進度を揃えることは当然のことだと思います。
ですが、ごく稀に、「あるクラスにだけ言い忘れていたこと」をうっかり出題してしまう先生がいます。
確かに、何度も同じ授業をしていると、どのクラスに何を伝えたのかを忘れてしまうこともありますが、それをテストに出してしまうと大問題です。
心配であれば、テストに出題する内容がちゃんと全クラスに伝わっているか事前に確認しておくと良いと思います。
また、テスト前になると、テストに何が出るのかを探ってくる生徒もいます。
その際にうっかり口を滑らせ、重要な事柄を伝えてしまったら、必ず同じことを全員に伝えるようにします。
生徒によって利益・不利益が出ないよう配慮することも大切です。
・過去問のコピペはNG!
音楽のように授業数が少なく、さらに全学年の授業を毎年担当していると、正直ネタが尽きてしまいます…
だからと言って、過去に出題した問題をそのまま引用するのはNGです。
生徒は、先輩に頼めば簡単に過去問を手に入れることができますし、「○○先生の何年分の過去問」というように塾がストックしている場合もあります。
同じ学校に長く勤務しているとだんだん出題することがなくなって苦しくなりますが、出題方法や形式を変えるなどして対応すると良いです。
・早い段階から作成に取り掛かる!
テストの直前に慌てて作るとミスする可能性が高いですし、学校によっては起案(管理職のチェック)が必要な場合があります。
早めにテストの作成に取り掛かれると良いと思います。
まとめ
さて、この記事では定期テストの作り方やポイント、注意点をご紹介しました。
少しでも参考になっていれば幸いです。
続きを見る
採点業務のコツを伝授!定期テストを早く正確に丸付けする方法
\各教材の進め方や活動例はこちら/