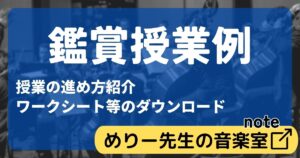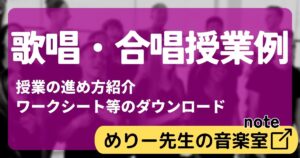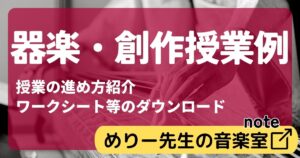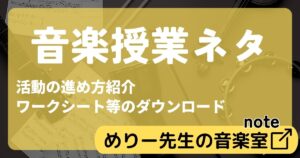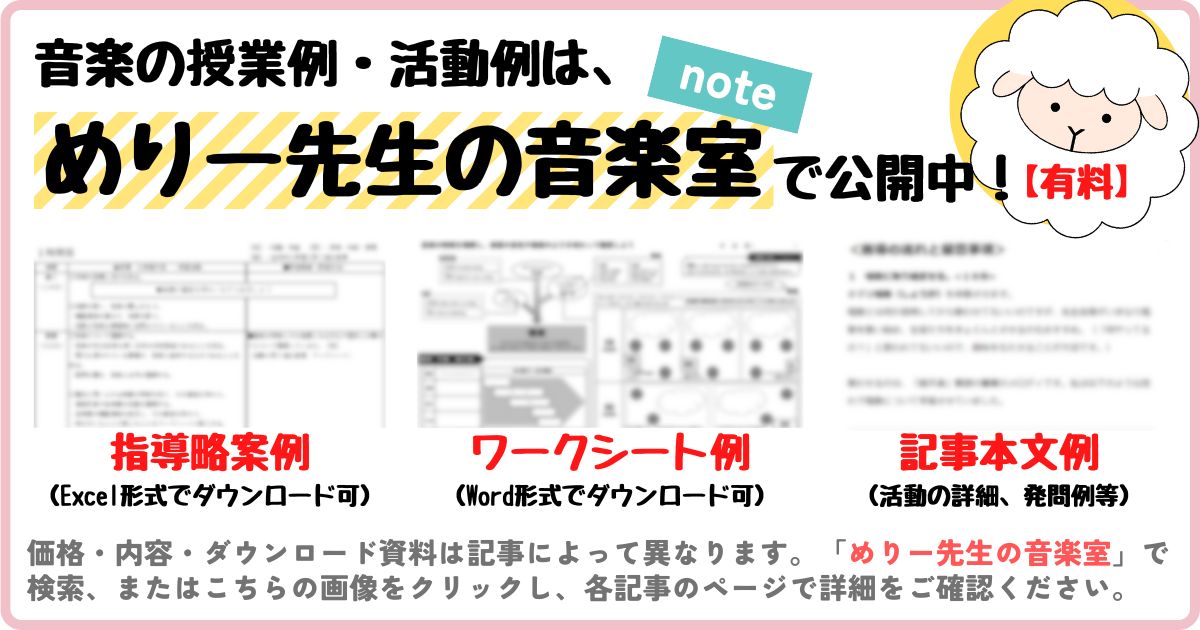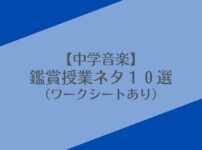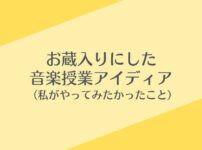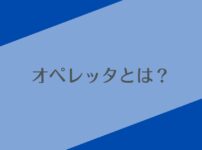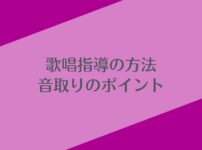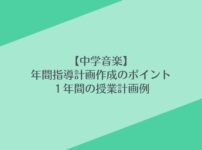この記事では、私が鑑賞授業を行う際に、特に意識していたことをご紹介します。
あくまで私の経験に基づく内容にはなりますが、授業の進め方にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。
※鑑賞授業に限らず、音楽授業全般に関することはこちらの記事にまとめているので、ご興味のある方は、合わせてご覧ください。
-

楽しい音楽授業を実現するためのポイント(私が意識していたこと)
続きを見る
鑑賞授業の7つのコツ
①教材ありきの授業にしない
鑑賞授業を行う際に、教材を決めてから目標を考えるというような、教材ありきの授業になってしまっていませんか?
ですが、大事なのは題材目標を達成できるかどうかであり、使用する教材は本来は何でも良いはずなのです。
「教科書に載っているから」という理由で教材研究をするのではなく、まずは一度なぜこの教材を扱うのかということについて考えてみると良いと思います。
②音楽との出会いを演出する
初対面の人とどのように出会ったかで、その人の印象が決まるように、音楽との出会い方によって、その音楽に対する印象や興味、関心が変わる気がします。
ゆえに、授業で新しい音楽を扱う際には、その出会い方を工夫する必要があると私は考えます。
授業の始めに「今日の授業で勉強する曲はこれです!」と言って音楽を流すのではなく、例えば、
・先生がいきなり演奏し始める
・授業前(生徒が入室してきたとき)から流しておく
・音楽を聴いてみたくなるような話をする
など工夫して、生徒と音楽との出会いを演出してあげると良いと思います。
私は「展覧会の絵」を扱う際には、音楽室の壁に絵を貼り、美術館に来たかのような空間を演出していました。
「展覧会の絵」を主教材とした授業の進め方やワークシートは以下のnote(有料)で紹介しています。
③「知覚」と「感受」を結び付けさせる
鑑賞して感想を書いて終わり!という授業は、正直あまり意味がないと私は思っています。
そう感じた理由は何なのか、音楽の諸要素がどう作用しているのかを考えさせることが、「知覚」「感受」両方の側面から音楽を理解するために必要です。
そのようなことを意識した活動を取り入れるのはもちろんのこと、ワークシートを作る際にも「聴き取ったこと」と「感じ取ったこと」を結び付けられるような欄を設けると良いと思います。
ワークシートの作り方は以下の記事で紹介していますので、よければ合わせてご覧ください。
-

音楽の授業におけるワークシートの作り方とポイント
続きを見る
④音楽を言語化するためのヒントを提供する
前述の通り、「知覚したこと」と「感受したこと」とのつながりを考えさせることは、音楽授業の基本です。
ですが、その曲にどのような要素があって、それによってどのような感じを受けるのかということを言葉で表現するのが苦手な生徒はいます。
そうした生徒を置き去りにするわけにはいかないので、「音楽を表す言葉」を一覧プリントにして配布するなど、音楽を言語化するためのヒントを事前に提示すると良いと思います。
また、音楽に対する考え方をしっかりと言葉で表現するには、ある程度トレーニングが必要です。
教科書掲載曲とは別に、毎時間3~5分程度の音楽を聴かせて、ひとこと感想を書かせるなど、言語化する活動を積極的に取り入れるのがおすすめです。
詳しくは以下の記事で紹介していますので、よければ合わせてご覧ください。
-

毎回の授業が楽しみになる「5分間ミュージック」(音楽授業ネタ)
続きを見る
⑤アクティブな動きを取り入れる
正直なところ、静かに音楽を鑑賞させて感想を書かせるだけの授業は面白いものではありません。
例えば、
・音楽から得たイメージを絵で表す
・音楽に合わせて体を動かす
・音が聴こえなくなったら手を下げる
など、鑑賞授業にも活動的な動きを取り入れた方が、生徒たちは「授業が楽しい」と感じるはずです。
一見音楽とは関係のなさそうな活動でも役に立つ場合があるので、日頃から授業のネタ集めは欠かせないなと思います。
⑥生徒の意見は否定も肯定もしない
鑑賞後に「感じ取ったこと」を生徒に発表してもらう場面があると思いますが、先生は否定も肯定もしないのがマストだと私は思っています。
というのも、音楽の感じ方は人それぞれで、「感じ取ったこと」に正解はないからです。
先生が「それは違うかな?」「その通り!」などと意見を否定・肯定すれば、生徒は音楽の授業での正解を探すようになってしまいます。
それでは、学校で音楽を学ぶ意味がなくなるので、生徒の意見を全て受け入れるつもりで、授業を進めるのが良いと思います。
また、言葉で返さずとも、生徒の意見を聞いて笑ったり、怪訝そうな顔をしたりすれば、生徒はすぐに気が付くので、ちょっとした表情も意識して授業するよう、私は心がけていました。
⑦自分の価値観を押し付けない
前述の通り、音楽の感じ方は人によって違うので、曲を聴かせた後に「この曲はこんなイメージだよね」などと自分の考えを伝えるのはNGです。
鑑賞授業の目標は「曲が作られた背景を理解して鑑賞しよう」など抽象的なものが多く、決して「曲が悲しい気持ちを表現していることに気が付こう」のように具体的かつ断定的なものではありません。
一見分かりづらいですが、それが音楽授業の面白いところです。
同じ音楽を、同じ時間、場所で聴いたとしても感じ方は異なるので、その意見の相違を楽しむことこそ、学校で音楽を学ぶ醍醐味なのではないでしょうか。
ゆえに、ゴールは見据えつつも、決して個人の価値観に偏らない授業を行うよう心がけることが大切だと思います。
まとめ
さて、この記事では私が鑑賞授業を行う際に意識していたことをご紹介しました。
少しでもお役に立てていれば幸いです。
関連記事
-

日本の伝統芸能を音楽の授業で扱う際のポイント
続きを見る

note「めりー先生の音楽室」へ
音楽の授業に役立ちそうなもの等を紹介しています!
↓ ↓ ↓


鑑賞授業
2025/3/21
【中学音楽】鑑賞授業ネタ10選(ワークシートあり)
元中学校音楽教員めりーです。 もうすぐ新年度!ということで、note「めりー先生の音楽室」で公開中の記事の中から、特に人気の鑑賞授業例10記事を厳選してご紹介します。 いずれも中学校の鑑賞授業でマスト!と言っても過言ではない題材・教材なので、お役立ていただけたら幸いです。 目次中学音楽 鑑賞授業ネタ10選①「魔王」(中学1年)②「四季」より「春」(中学1年)③【雅楽】(中学1年)④「交響曲第5番ハ短調(運命)」(中学2年)⑤「フーガ ト短調」(中学2年)⑥「勧進帳」(中学2年)⑦【オペラ】(中学2年)⑧「 ...
ReadMore

授業ネタ
2025/3/21
お蔵入りにした音楽授業アイディア(私が教員時代にやってみたかったこと)
元中学校音楽教員めりーです。 私には、教員時代に思い付いたものの出来なかった授業や、教員を辞めてからふと思い付いた授業アイディアがいくつかあります。 今はもう教員を辞めてしまい実践は不可能ですが、このアイディアが先生方のお役に立てるのでは?と思い、ブログに書き留めることにしました。 学習指導要領や教科書、年間指導計画などは抜きにして、単純に「こんな音楽の授業をやってみたかった!」という内容ですので、参考にされる際には自己責任でお願いします。 目次私がやってみたかった授業アイディア・絵に合う音楽を選んでディ ...
ReadMore

授業の基本
2025/3/21
音楽授業の必要性について。元教員が考える「学校で音楽を学ぶ理由」
元中学校音楽教員めりーです。 時折耳にする「音楽の授業はいらない」という意見…元音楽教員としては少し複雑な気持ちになります。 というわけで、今回は永遠のテーマとも言える「なぜ学校で音楽を学ぶのか」について私なりの思いをまとめてみます。 一個人の意見ではありますが、音楽の先生方は、生徒から「どうして音楽の授業が必要なの?」と聞かれることもあると思うので、そんなときの受け答えのヒントとしていただければ幸いです。 目次将来役に立ててほしいから音楽の授業があるわけではない私が思う「学校で音楽を学ぶ理由」①様々な音 ...
ReadMore

鑑賞授業
2025/3/21
オペレッタとは?オペラとの違いや有名な曲も合わせて解説
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、オペレッタとは何かについて、オペラとの違いやそれぞれの代表曲と合わせて解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 目次オペラとは?オペレッタとは?オペレッタとオペラの違いは?オペレッタの有名な曲2選①「こうもり」序曲①「天国と地獄」序曲まとめ オペレッタについて説明する前に、まずはオペラについてです。 オペラとは? オペラは歌を中心に物語が進む歌劇のことです。 演劇と同じように、華やかな衣装に身を包んだ出演者が舞台上で ...
ReadMore

自習課題
2025/6/5
noteで公開中の自習プリント(中学音楽)を紹介します!
元中学校音楽教員めりーです。 急に音楽の授業が行えなくなった場合に役立つ自習プリント。 「いざという時のために用意しておきたいけど、忙しくて作る暇がない」という先生も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では、noteで公開中の授業資料から、すぐに使える音楽の自習プリントをご紹介します。 いずれも有料にはなりますが、一度購入していただければ長く使えるので、お役立ていただければ幸いです。 目次まずはこれ!音楽の自習プリント音楽記号・用語一覧プリント練習問題付き!楽典まとめプリントお楽しみ課題!クロスワ ...
ReadMore

歌唱授業
2025/3/21
音楽授業における歌唱指導の方法・音取りのポイント
元中学校音楽教員めりーです。 音楽の授業で必ず行う歌唱指導。 にもかかわらず、どのような流れで進めるのか、どのように音取りを行うのかといった具体的な指導法は誰も教えてくれないですよね。 そこで、この記事では私の歌唱指導の方法をご紹介します。 あくまで私の進め方であり、「これが正解!」というわけではありませんが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。 目次歌唱指導って何するの?歌唱指導(音取り)の基本的な流れ1時間目の流れ2時間目以降の流れ歌唱指導(音取り)のコツコツ①常に全員でなくても良いコツ②表現の工夫 ...
ReadMore

授業の基本
2024/7/24
【中学音楽】年間指導計画作成のポイントと1年間の授業計画例
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、年間指導計画作成のポイントと、1年間の授業計画(例)をご紹介します。 あくまで私が勤務していた頃の話にはなってしまいますが、参考にしていただければ幸いです。 目次年間指導計画作成のポイント①年間の授業時数を意識する②学校行事を確認する③評価の時期から逆算する1年間の授業計画例中学1年音楽 授業計画例中学2年音楽 授業計画例中学3年音楽 授業計画例(補足1)各題材で扱う教材について(補足2)実技テストについてまとめ 年間指導計画作成のポイント まずは、私が年間指導 ...
ReadMore

授業ネタ
2025/3/21
盛り上がる!音楽授業におすすめのゲーム「歌詞ビンゴ」
元中学校音楽教員めりーです。 音楽授業に取り入れると盛り上がりそうな、簡単なゲーム活動例を思い付いたので、ご紹介します。 その名も「歌詞ビンゴ」です。 授業のスキマ時間やお楽しみ会などに取り入れられるのでは?と思うので、参考にしていただければ幸いです。 目次歌詞ビンゴとは?歌詞ビンゴの進め方①ビンゴカードの作成・配布②曲を流してビンゴ大会!まとめ 歌詞ビンゴとは? 歌詞ビンゴは、その名の通り歌の歌詞を活用したビンゴゲームです。 所要時間は10分~30分で、準備もそんなに必要ないので、「少し時間が余りそうだ ...
ReadMore