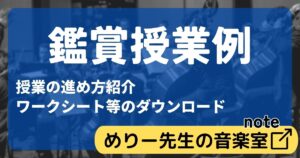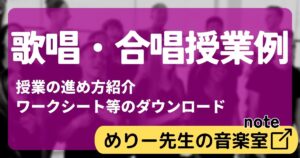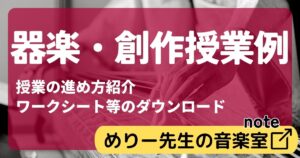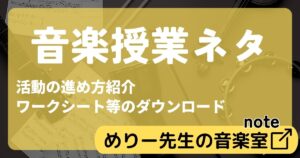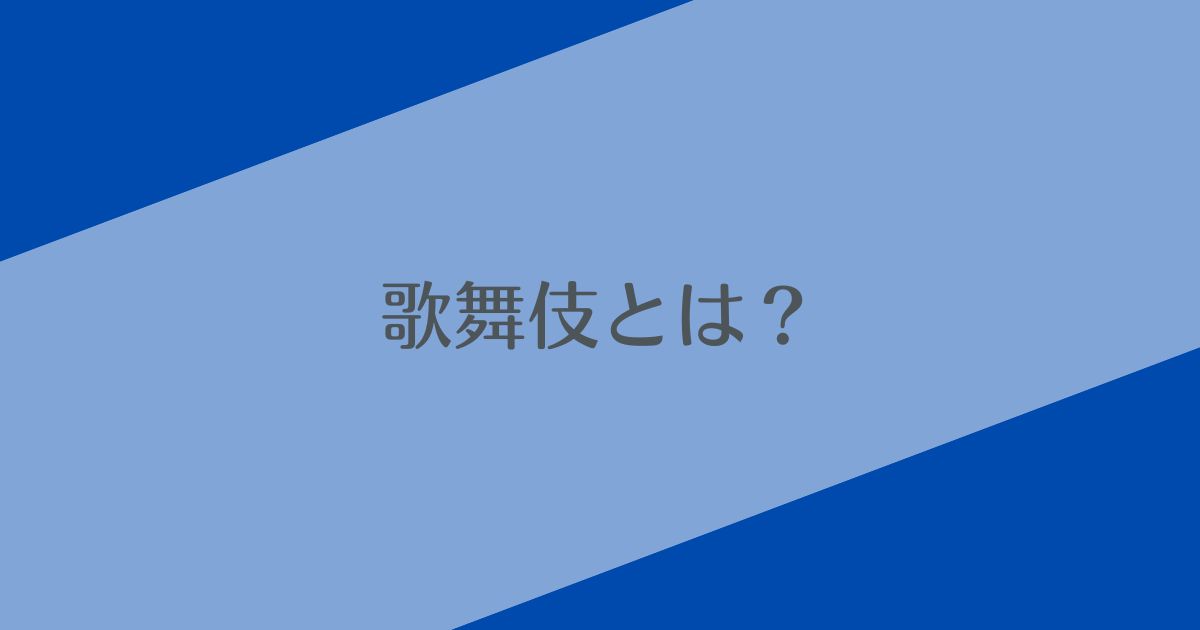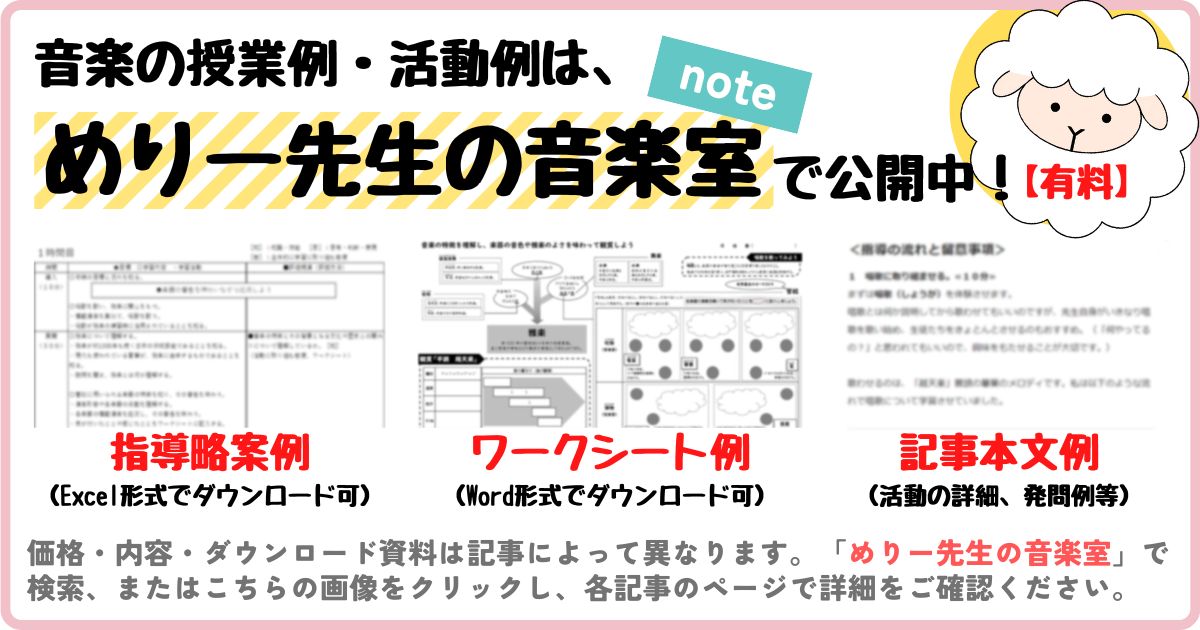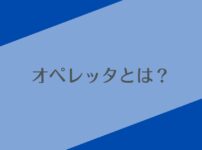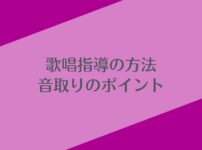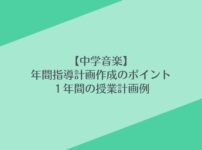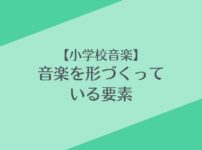この記事では、私が授業で説明していたこと等を基に、歌舞伎についてざっくり解説し、簡単な授業例をご紹介します。
説明内容も授業例も「私だったらこうするよ」という内容ですが、少しでも参考になれば幸いです。
歌舞伎についてまとめたプリントは以下のnote(有料)で紹介しています。
歌舞伎とは?
歌舞伎は、音楽、舞踊、演技が一体となってできた総合芸術のことです。
歌=音楽、舞=舞踊、伎=演技と覚えるのがおすすめです。
出雲阿国が1603年頃に創始したとされる「かぶき踊」が元祖とされ、様々な社会的事象や芸術の影響を受けながら発展してきた伝統芸能です。
授業でおさえたい、歌舞伎の特徴
ここからは、歌舞伎を授業で扱う際に最低限おさえておきたい事項をピックアップしてご紹介します。
・歌(音楽)の特徴
歌舞伎の音楽は、伴奏音楽と効果音の2種類に分けられるので、それぞれの特徴や役割を簡単にご紹介します。
伴奏音楽:歌舞伎音楽を代表する4つ
伴奏音楽には、長唄、常磐津節、清元節、義太夫節(竹本)の4つがあり、演目によってどの音楽を用いるかは異なります。
それぞれの音楽によって、使用する三味線(太棹・中棹・細棹)や音楽的特徴が違うので、いろいろと聴き比べるのも面白そうです。
効果音:黒御簾音楽
歌舞伎では、足音や自然の音など効果音も生演奏で行われています。
舞台下手の黒御簾と呼ばれる部屋の中で役者の動きに合わせて演奏しているので、「黒御簾音楽(くろみすおんがく)」と呼ばれています。
・舞(舞踊)の特徴
舞踊は所作事とも言われ、元々は「女形」が演じるものでしたが、今では様々なキャラクターが時にたくましく、時に美しい舞を舞うことで、歌舞伎の物語を盛り上げています。
「勧進帳」で弁慶が酒宴の席で舞う「延年の舞」が有名です。
・伎(演技)の特徴
細かい動きやしぐさなど、様々な特徴がありますが、ここでは最低限押さえておきたい2つの型をご紹介しておきます。
見得(みえ)
重要な場面や、登場人物の気持ちの高まりを表現したい時に行われる、役者が一瞬静止し、観客に強い印象を与える型を「見得(みえ)」と言います。
歌舞伎と言ったらコレ!というくらい歌舞伎らしさ全開の演技ですよね。
「元禄の見得」や「石投げの見得」など、演目によって様々な型が存在します。
六方(ろっぽう)
歩いたり走ったりするときの手足の動きを誇張して美しく表現する演技のことを「六方(ろっぽう)」と言います。
役者が花道を退場する時などに用いられることが多いです。
"天・地・東・西・南・北の六方向に手足を動かす"と覚えると漢字を間違えなくて済みます!
・その他の特徴
隈取(くまどり)
歌舞伎が、他の芸能と明らかに違うのは、何と言っても役者の化粧だと思います。
顔の血管や筋肉を誇張するための独特な化粧法のことを「隈取(くまどり)」と言います。
正義の味方は赤色、人間以外の不気味な存在は青色など、登場人物によって化粧の色が異なることもあるようです。
舞台装置の工夫
「花道」や「せり」「廻り舞台」など様々な舞台の仕掛けや演出が楽しめるのも、歌舞伎の魅力のひとつです。
歌舞伎の授業例
さて、歌舞伎についてざっくりご説明しましたが、ここからは歌舞伎を題材とする場合の授業例2パターンを簡単にご紹介します。
あくまで「こんな授業はいかがでしょうか?」という提案ですので、参考程度に読んでいただければ幸いです。
①物語展開に焦点を当てた授業
ストーリー展開も歌舞伎の魅力のひとつなので、そこに着目することで、歌舞伎に対する興味をもたせることができるのでは?と思います。
ゆえに、私は、1時間目に歌舞伎について簡単に説明した後、2時間目に「勧進帳」を、登場人物がどのような行動を起こすのかを予想しながら鑑賞させるといった流れの授業を行ったことがあります。
私が過去に行った授業をブラッシュアップ(授業資料も新たに作成)し、こちらのnote(有料)で公開しているので、「詳しく知りたい」という方はこちらをご覧いただければ幸いです。
②能、文楽との比較授業
同じ伝統芸能である能や文楽とは互いに影響を受け合いながら発展してきたので、比較鑑賞を通して文楽の特徴や魅力を探る授業も良さそうです。
例えば、4時間扱いで、1時間目~3時間目は各芸能を様々な観点で比較し、4時間目にいずれかの芸能についてまとめるという流れはいかがでしょうか?
比較鑑賞がメインなので広く浅くの内容になってしまいますが、伝統芸能に興味をもってもらうことにはつながりそうです。
この授業例はnote(有料)で公開しているので、ご興味がある方はご覧いただければと思います。
まとめ
さて、歌舞伎の簡単な解説と授業例は以上です。
かなりざっくりとした内容にはなってしまいましたが、少しでもお役に立てていれば幸いです。
関連記事
-

歌舞伎「勧進帳」のあらすじを元中学校音楽教員がざっくり解説
続きを見る

note「めりー先生の音楽室」へ
音楽の授業に役立ちそうなもの等を紹介しています!
↓ ↓ ↓


授業の基本
2024/7/24
音楽授業の必要性について。元教員が考える「学校で音楽を学ぶ理由」
元中学校音楽教員めりーです。 時折耳にする「音楽の授業はいらない」という意見…元音楽教員としては少し複雑な気持ちになります。 というわけで、今回は永遠のテーマとも言える「なぜ学校で音楽を学ぶのか」について私なりの思いをまとめてみます。 一個人の意見ではありますが、音楽の先生方は、生徒から「どうして音楽の授業が必要なの?」と聞かれることもあると思うので、そんなときの受け答えのヒントとしていただければ幸いです。 目次将来役に立ててほしいから音楽の授業があるわけではない私が思う「学校で音楽を学ぶ理由」①様々な音 ...
ReadMore

鑑賞授業
2024/7/24
オペレッタとは?オペラとの違いや有名な曲も合わせて解説
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、オペレッタとは何かについて、オペラとの違いやそれぞれの代表曲と合わせて解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 目次オペラとは?オペレッタとは?オペレッタとオペラの違いは?オペレッタの有名な曲2選①「こうもり」序曲①「天国と地獄」序曲まとめ オペレッタについて説明する前に、まずはオペラについてです。 オペラとは? オペラは歌を中心に物語が進む歌劇のことです。 演劇と同じように、華やかな衣装に身を包んだ出演者が舞台上で ...
ReadMore

自習課題
2024/7/24
noteで公開中の自習プリント(中学音楽)を紹介します!
元中学校音楽教員めりーです。 急に音楽の授業が行えなくなった場合に役立つ自習プリント。 「いざという時のために用意しておきたいけど、忙しくて作る暇がない」という先生も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では、noteで公開中の授業資料から、すぐに使える音楽の自習プリントをご紹介します。 いずれも有料にはなりますが、一度購入していただければ長く使えるので、お役立ていただければ幸いです。 目次まずはこれ!音楽の自習プリント音楽記号・用語一覧プリント練習問題付き!楽典まとめプリントお楽しみ課題!クロスワ ...
ReadMore

歌唱授業
2024/7/24
音楽授業における歌唱指導の方法・音取りのポイント
元中学校音楽教員めりーです。 音楽の授業で必ず行う歌唱指導。 にもかかわらず、どのような流れで進めるのか、どのように音取りを行うのかといった具体的な指導法は誰も教えてくれないですよね。 そこで、この記事では私の歌唱指導の方法をご紹介します。 あくまで私の進め方であり、「これが正解!」というわけではありませんが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。 目次歌唱指導って何するの?歌唱指導(音取り)の基本的な流れ1時間目の流れ2時間目以降の流れ歌唱指導(音取り)のコツコツ①常に全員でなくても良いコツ②表現の工夫 ...
ReadMore

授業の基本
2024/7/24
【中学音楽】年間指導計画作成のポイントと1年間の授業計画例
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、年間指導計画作成のポイントと、1年間の授業計画(例)をご紹介します。 あくまで私が勤務していた頃の話にはなってしまいますが、参考にしていただければ幸いです。 目次年間指導計画作成のポイント①年間の授業時数を意識する②学校行事を確認する③評価の時期から逆算する1年間の授業計画例中学1年音楽 授業計画例中学2年音楽 授業計画例中学3年音楽 授業計画例(補足1)各題材で扱う教材について(補足2)実技テストについてまとめ 年間指導計画作成のポイント まずは、私が年間指導 ...
ReadMore

授業ネタ
2024/7/24
盛り上がる!音楽授業におすすめのゲーム「歌詞ビンゴ」
元中学校音楽教員めりーです。 音楽授業に取り入れると盛り上がりそうな、簡単なゲーム活動例を思い付いたので、ご紹介します。 その名も「歌詞ビンゴ」です。 授業のスキマ時間やお楽しみ会などに取り入れられるのでは?と思うので、参考にしていただければ幸いです。 目次歌詞ビンゴとは?歌詞ビンゴの進め方①ビンゴカードの作成・配布②曲を流してビンゴ大会!まとめ 歌詞ビンゴとは? 歌詞ビンゴは、その名の通り歌の歌詞を活用したビンゴゲームです。 所要時間は10分~30分で、準備もそんなに必要ないので、「少し時間が余りそうだ ...
ReadMore

鑑賞授業
2024/7/24
歌舞伎「勧進帳」のあらすじを元中学校音楽教員がざっくり解説
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、歌舞伎の有名な演目「勧進帳」のあらすじを簡単にご紹介します。 音楽を勉強中の方や、授業準備中の先生方の参考になれば幸いです。 目次「勧進帳」基本情報「勧進帳」主な登場人物(相関図)「勧進帳」あらすじ解説①役者の登場②勧進帳の読み上げ③山伏問答④弁慶の驚くべき作戦⑤主従の絆の深さ⑥延年の舞⑦役者の退場(飛び六方)まとめ 「勧進帳」を主教材とした鑑賞授業の進め方やワークシートは以下のnote(有料)で紹介しています。 「勧進帳」基本情報 作詞者:三世並木五瓶 作曲者 ...
ReadMore

授業の基本
2024/7/24
【小学校】音楽を形づくっている要素とは?ざっくり解説
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、小学校の学習指導要領で示されている音楽を形づくっている要素を簡単に解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 \中学校学習指導要領で示されている要素はこちら/ 目次音楽を形づくっている要素とは?音楽を特徴付けている要素音楽の仕組みまとめ 音楽を形づくっている要素とは? 小学校音楽科学習指導要領に示されている音楽を形づくっている要素は以下の通りです。 ア 音楽を特徴付けている要素 音色,リズム,速度,旋律,強弱,音の重な ...
ReadMore