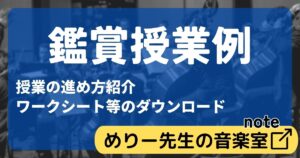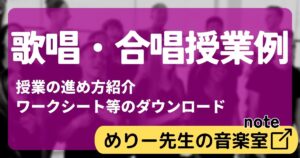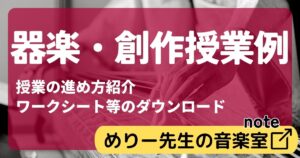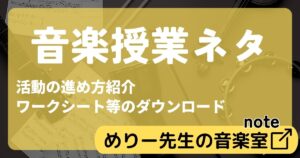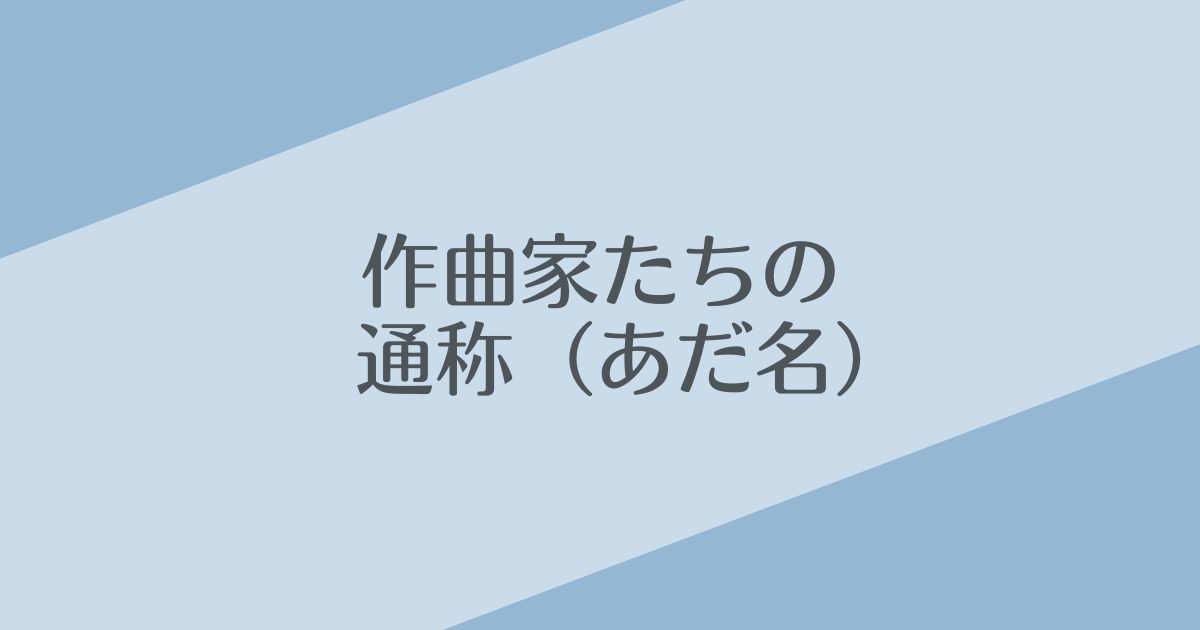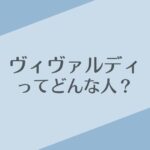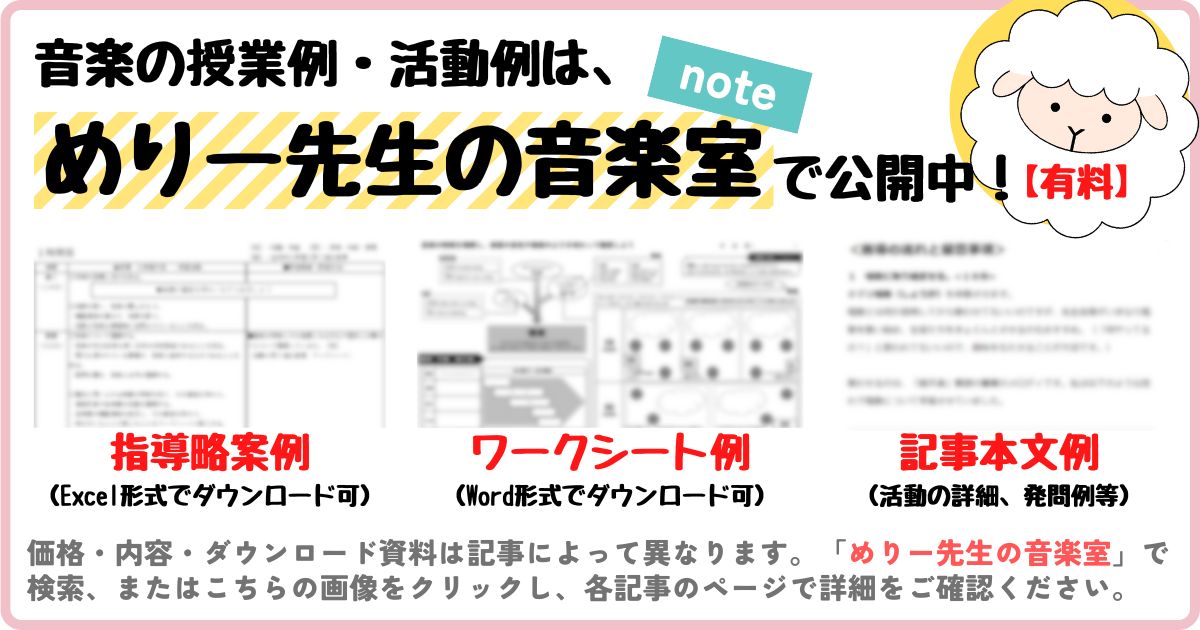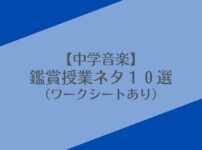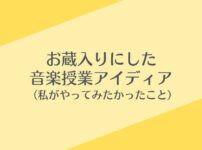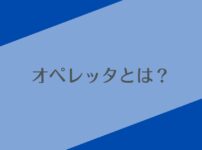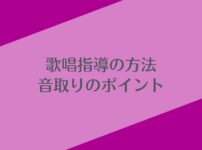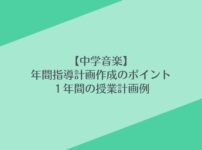歴史に名を残す作曲家たちには、通称(あだ名・呼び名)が付けられていることがあります。
たいていの場合、その偉大な功績から通称は付けられていますが、なぜそのようなあだ名で呼ばれるのだろう?と思うようなものも中にはありますよね。
そこで、この記事では、有名な作曲家12人の通称とその理由を誕生年順ご紹介します。
作曲家のあだ名に興味がある方や音楽の授業に使えそうな雑学をお探しの方の参考になれば幸いです。
※通称やその理由には諸説あります。
目次
ヴィヴァルディ=協奏曲の父
1678年、イタリアに生まれたアントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ。
彼は作曲家、ヴァイオリニスト、講師、司祭と様々な顔をもつ、バロック時代に活躍した音楽家の一人です。
カツラを脱ぐと赤毛だったことから「赤毛の司祭」というあだ名で呼ばれていたようですが、「四季」などの数々の協奏曲を世に輩出したことから、「協奏曲の父」と称されることもあります。
-

ヴィヴァルディってどんな人?あだ名やエピソード、代表曲
続きを見る
バッハ=音楽の父
1685年に生まれたドイツの作曲家、ヨハン・セバスティアン・バッハ。
バロック時代の作曲家ですが、当時のバロック音楽と言えばオペラや協奏曲などイタリアで誕生したものが主流。
そんなイタリアで発展した音楽をドイツで取りまとめ、技法やルールを整えるなど西洋音楽の基礎を築いたということで「音楽の父」と呼ばれるようになりました。
また、バッハ一族には音楽家が多く、他のバッハと区別するために、「大バッハ」と呼ばれることもあります。
ヘンデル=音楽の母
バッハと同じく、1685年に生まれたバロック時代の作曲家、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。
彼はドイツで生まれ、イタリアで成功したのち、経済大国だったイギリスで市民向けに演奏会などを催行しました。
男性なのにどうして「音楽の母」なの?と思うかもしれませんが、これは同時期に活躍したバッハ(音楽の父)と対等な存在であることを示す呼び名として、日本で名づけられたからだそうです。
ハイドン=交響曲の父・弦楽四重奏曲の父
フランツ・ヨーゼフ・ハイドンは1732年に生まれた、古典派を代表するオーストリアの作曲家です。
数多くの交響曲や弦楽四重奏曲を作曲し、ベートーヴェンなど後の音楽家たちが彼の作品を手本にしたことから「交響曲の父」または「弦楽四重奏曲の父」と呼ばれています。
同じウィーン出身のモーツァルトがハイドンを尊敬していたり、ベートーヴェンが彼に弟子入りした時期があったりと、作曲家たちの憧れの存在だったようです。
モーツァルト=神童
1756年、オーストリアに生まれた古典派を代表する作曲家、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト。
5歳で作曲を始め、36歳で亡くなるまでに、西洋音楽のあらゆるジャンルで傑作を遺した天才であることから「神童」と称されています。
ちなみに、ミドルネームの「アマデウス」は「神に愛される」という意味だそうで、名前からして「神童」感が漂っています。
ベートーヴェン=楽聖
1770年にドイツに生まれたルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、古典派を代表する作曲家で、その名を知らない人はいないと言っても過言ではありません。
数々の名曲を生み出しただけでなく、音楽界に遺した偉大な功績は数知れず…
そんな彼を称え、日本では"音楽の聖人"を意味する「楽聖」と呼ばれることがあります。
シューベルト=歌曲王
1797年にオーストリアに生まれたフランツ・ペーター・シューベルト。
ロマン派を代表する作曲家の一人です。
31歳の若さで亡くなるまで、600曲以上のリート(ドイツ語による歌曲)を生み出したことから「歌曲の王」と称されています。
ヨハン・シュトラウスⅠ世=ワルツの父
1804年に生まれ、オーストリアで活躍した音楽家、ヨハン・シュトラウスⅠ世。
「ラデツキー行進曲」などのワルツ曲を多く作曲したことから、生前は「ワルツ王」と呼ばれていましたが、死後、その呼び名は息子のヨハン・シュトラウスⅡ世に継承され、彼は「ワルツの父」と呼ばれるようになりました。
ショパン=ピアノの詩人
1810年にポーランドに生まれたフレデリック・フランソワ・ショパン。
ピアニストとして活躍しながら、美しい旋律と和声を特徴としたピアノ曲を数多く作曲し、ピアノの表現の幅を広げたことから「ピアノの詩人」と称されています。
リスト=ピアノの魔術師
1811年、ハンガリー(オーストリア占領下)に生まれたフランツ・リストは、ピアニストとして活躍する傍ら作曲家や指導者としての顔ももっていた音楽家です。
ショパンと同時期に活躍したため、比較されることの多い2人ですが、リストの特徴は何と言っても超絶技巧です。
当時No.1の技術をもっていた彼(しかもイケメン!)のサロンコンサートでは女性が失神したという逸話まで残っており、そんなエピソードから「ピアノの魔術師」と呼ばれるようになりました。
ヨハン・シュトラウスⅡ世=ワルツ王
1825年、ヨハン・シュトラウスⅠ世の長男として生まれ、オーストリアで作曲家として活躍した、ヨハン・シュトラウスⅡ世。
ワルツやポルカなどを数多く作曲し、当時は一世を風靡しました。
父から継承した「ワルツ王」という呼び名の他にも「ウィーンの太陽」、「ウィーンのもう1人の皇帝」などと呼ばれることもあったようです。
ラヴェル=管弦楽の魔術師
1875年にフランスに生まれた作曲家、ジョゼフ・モーリス・ラヴェル。
彼の代表曲「ボレロ」を聴くとそのすごさが分かるのですが、様々な楽器の良さや特徴が生きる曲作りをしている点が、「管弦楽の魔術師」と言われる理由かと思います。
また、そのあまりにも精緻な楽曲を称え、ロシアの作曲家ストラヴィンスキーが「スイスの時計職人」と称したという逸話も残っています。
まとめ
さて、今回は有名な作曲家たちの通称をご紹介しました。
通称(あだ名)とその理由には諸説ありますが、少しでも参考になっていれば幸いです。
続きを見る
【クラシック音楽史】ざっくりとした流れを元音楽教員が解説
\各教材の進め方や活動例はこちら/