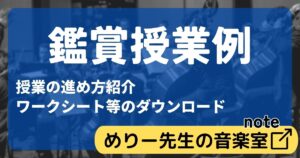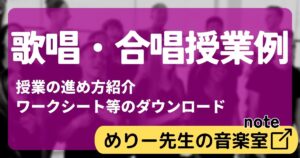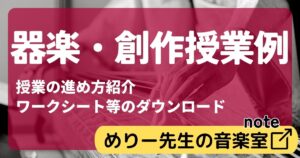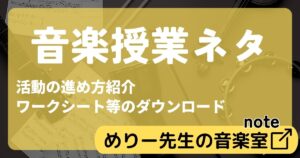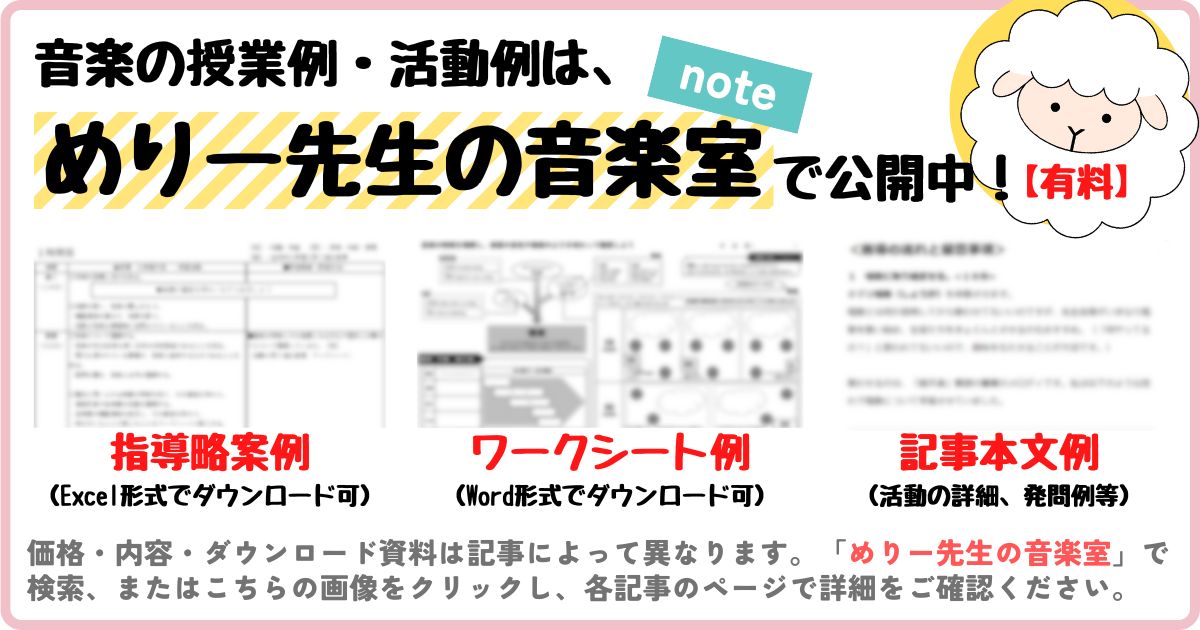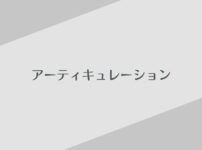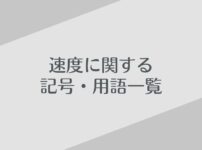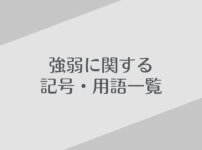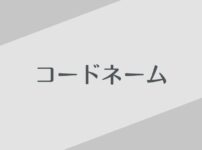この記事では、性格的小品(キャラクターピース)のひとつである、ラプソディの意味や特徴、代表曲をざっくりとご紹介します。
※性格的小品(キャラクターピース)とは、自由な発想によって作られた、ピアノのための短い楽曲の総称です。(詳しくは以下の記事をご覧ください)
-

性格的小品(キャラクターピース)とは?主な種類と特徴まとめ
続きを見る
ラプソディとは?
ラプソディは、日本語では狂詩曲(きょうしきょく)と訳される、民族的または叙事的な内容を自由な形式で表現した曲のことです。
ロマン派時代以降に多く作られ、高揚した感情を情熱的に表現するのが特徴で、様々な曲調や既存のメロディを取り入れているものもあります。
-

ロマン派音楽のポイント(特徴と代表的な作曲家)をざっくり解説
続きを見る
ラプソディの代表的な作品「ハンガリー狂詩曲第2番」
ラプソディと言えば、リスト作曲の「ハンガリー狂詩曲」が有名です。
曲名の通り、リストは祖国ハンガリーの古くからある民謡をモチーフにしたつもりですが、実は民謡ではなく割と新しい音楽で、作曲された当時から「リストは勘違いしている」と言われていたらしいです。
それでも、クラシック音楽の名曲であることには変わりありません。
「ハンガリー狂詩曲」は全部で19曲ありますが、特に「第2番 嬰ハ短調」は有名なので、聴いたことがある方も多いのではないでしょうか。
1曲の中に様々な表情が見られる聴きごたえ抜群の作品で、カデンツァ部分もあるので、編曲者や演奏者による違いも楽しめます。
ラプソディの可能性を広げた「ラプソディ・イン・ブルー」
ラプソディを語る上で欠かせない名曲が、ガーシュイン作曲の「ラプソディ・イン・ブルー」です。
「ブルー」は青ではなくジャズのことで、直訳すると「ジャズによる狂詩曲」という意味になります。
ガーシュインはジャズをアメリカの民族音楽と考え、このような曲を作ったのかもしれません。
クラシック音楽とポピュラー音楽を融合した、非常に画期的な作品です。
まとめ
以上、この記事ではラプソディの意味や特徴、代表的な作品をご紹介しました。
かなりざっくりとした内容ではありましたが、少しでも皆さんのお役に立てていれば幸いです。
※ジャンル名をクリックすると各記事のページに飛びます。

note「めりー先生の音楽室」へ
音楽の勉強に役立ちそうなもの等を紹介しています!
↓ ↓ ↓


楽典・音楽用語
2025/6/24
楽典とは?最低限知っておくと役立つ11項目をざっくり解説!
元中学校音楽教員めりーです。 音楽を学んでいると、楽典という言葉を度々目にすると思いますが、そもそも楽典とはいったい何のことでしょうか? 今回は、そんな楽典について簡単にご説明するとともに、「最低限これだけは知っておくと役立つよ!」という基礎的な項目をご紹介します。 目次楽典とは?知っておくと役立つ、楽典の基礎項目①楽譜・五線譜②音名・階名③音符や休符④音階と調⑤拍と拍子⑥音程⑦和音⑧速度⑨強弱⑩反復記号⑪奏法に関する記号まとめ 楽典とは? 楽典とは、音楽の基礎的な理論のことで、演奏に役立つ記号や用語、楽 ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/6/3
ト音記号とヘ音記号って何?音部記号の役割についてざっくり解説!
元中学校音楽教員めりーです。 突然ですが、こちらの記号は何でしょう? きっと多くの方が「ト音記号」という名前を思い浮かべたと思います。 ですが、実際にこの記号がどんな役割を果たしているのかまでは知らないという方も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では「ト音記号」や「ヘ音記号」など、音部記号と呼ばれる記号の役割について簡単に解説します。 目次音部記号とは?ト音記号とヘ音記号譜表まとめ \本記事の内容を含むまとめプリントはこちら/ 音部記号とは? 五線譜に書かれる音符の高さを示す記号を音部記号と言い ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/6/3
楽譜とは?五線譜って何?元音楽教員がざっくり解説!
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、音楽を学ぶ上で必要不可欠な、楽譜の役割について、簡単に解説します。 そもそも楽譜や五線譜が何なのか分からないという方の参考になれば幸いです。 目次楽譜とは?五線譜とは?まとめ \本記事の内容を含むまとめプリントはこちら/ 楽譜とは? 音楽を音符や休符、記号などによって書き表したものを楽譜と言います。 楽譜には様々な種類がありますが、西洋音楽などで使われる以下のような五線譜が一般的です。 楽譜を見れば、どの音をどのくらいの長さ演奏するのかが分かります。 同時に、強 ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/5/16
アーティキュレーションとは?よく使われる記号や用語をざっくり解説
元中学校音楽教員めりーです。 音楽を勉強している方は「アーティキュレーション」という言葉を聞いたことがあるかと思います。 ですが、アーティキュレーションが何なのかよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか? そこで、この記事ではアーティキュレーションについての簡単な解説と、よく使われる記号・用語をご紹介します。 目次アーティキュレーションとは?よく使われる記号・用語まとめ アーティキュレーションとは? アーティキュレーションは、音と音のつなげ方や区切り方で、旋律に表情を付ける演奏技法のことで ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/5/16
譜読みの最初に要確認!速度記号・用語一覧(読み方と意味まとめ)
元中学校音楽教員めりーです。 今回は、速度に関する記号や用語をご紹介します。 楽譜上でよく見かける記号・用語のみをピックアップしているので、ざっくりとした説明にはなりますが、音楽を勉強中の方の参考になれば幸いです。 目次そもそも音楽における「速度」とは?速度記号・用語は楽譜のどこに書いてある?速度を表す記号・用語①数字で表す②ことばで表す速度の変化を指示する用語速さを次第に変化させるこれまでの速さと比較して指示する強弱の変化も同時に指示する変更した速度を戻す意味を補足する付加語・接尾語付加語接尾語速度に関 ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/5/16
fffとは?音楽に欠かせない強弱記号・用語一覧(読み方と意味まとめ)
元中学校音楽教員めりーです。 突然ですが、こちらの音楽記号は何と読むでしょうか? 「エフエフエフ?」…残念ながら違います。 答えは「フォルティッシッシモ(フォルテフォルティッシモ)」です。 この記号は、強弱記号のひとつなのですが、その意味や他の強弱記号との関係がよく分からないという方も多いのではないでしょうか? というわけで、今回は、強弱に関する記号・用語の読み方と意味をまとめてみました。 楽譜上でよく見かける記号・用語のみをピックアップして紹介するので、ざっくりとした説明にはなりますが、音楽を勉強中の方 ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/6/3
音名と階名の違いは?意味や役割をざっくり解説
元中学校音楽教員めりーです。 突然ですが、この音は何の音でしょう? ※ト長調とします これを「ソ」と呼ぶ方もいれば、「ド」と呼ぶ方もいると思いますが、どちらも正解です。 というのも、音には音名と階名という2つの呼び方があり、この音の場合、音名は「ソ」ですが、階名だと「ド」なのです。 …何を言っているのか、わけわからん! という方のために、この記事では音名と階名の違いを解説します。 目次音名とは?階名とは?まとめ \階名についてまとめたプリントはこちら/ 音名とは? 音名は、その名の通り音の名前です。 音楽 ...
ReadMore

楽典・音楽用語
2025/5/16
コードネームとは?仕組みをざっくり解説
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、楽器を演奏する際に使うコードネームについて解説します。 楽器を始めたばかりの方やテスト勉強中の学生さん、授業での説明にお困りの先生方のお役に立てれば幸いです。 ※初めての方でも分かりやすいように、音名ではなくハ長調の階名(ドレミファソラシ)を使って説明します。 目次コードネームとは?コードネームの仕組み①音名②三和音の種類③付け足す音④その他の特記事項まとめ コードネームとは? コードは「和音」、ネームは「名前」のことなので、コードネームとは、和音の名前(呼び方 ...
ReadMore