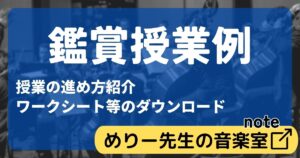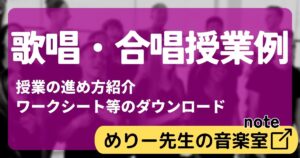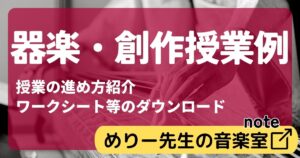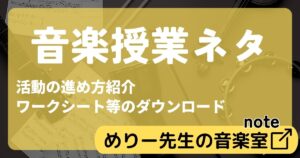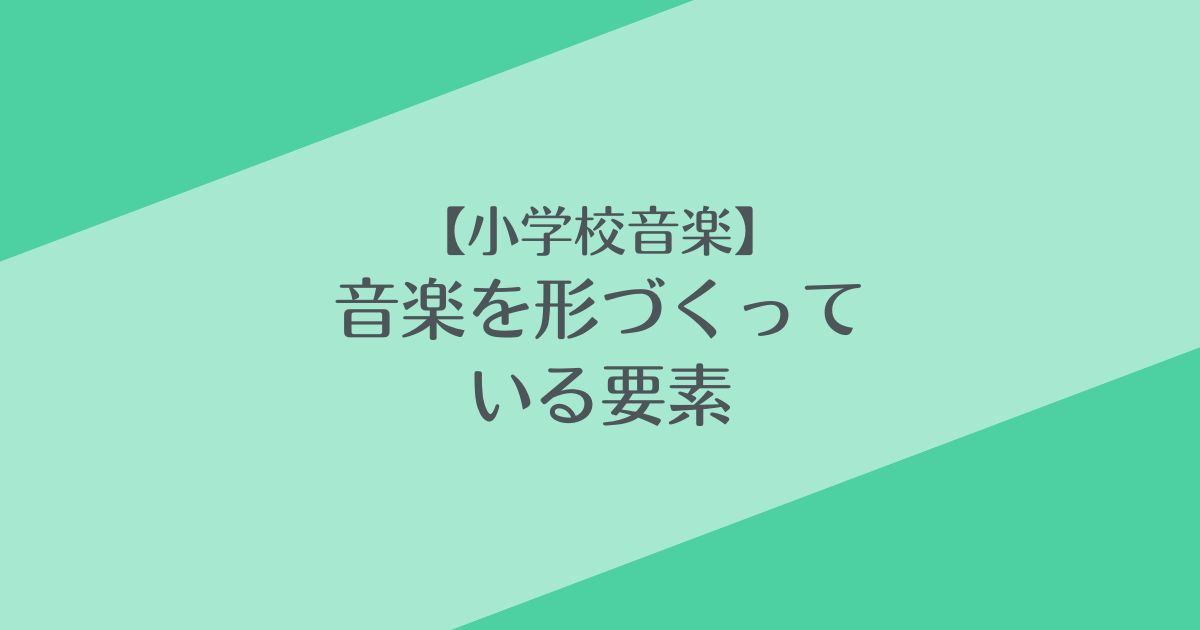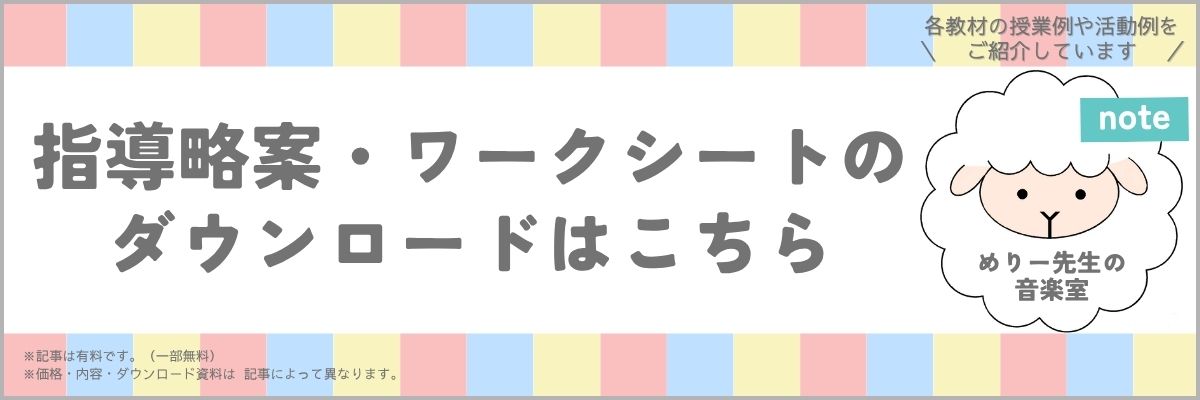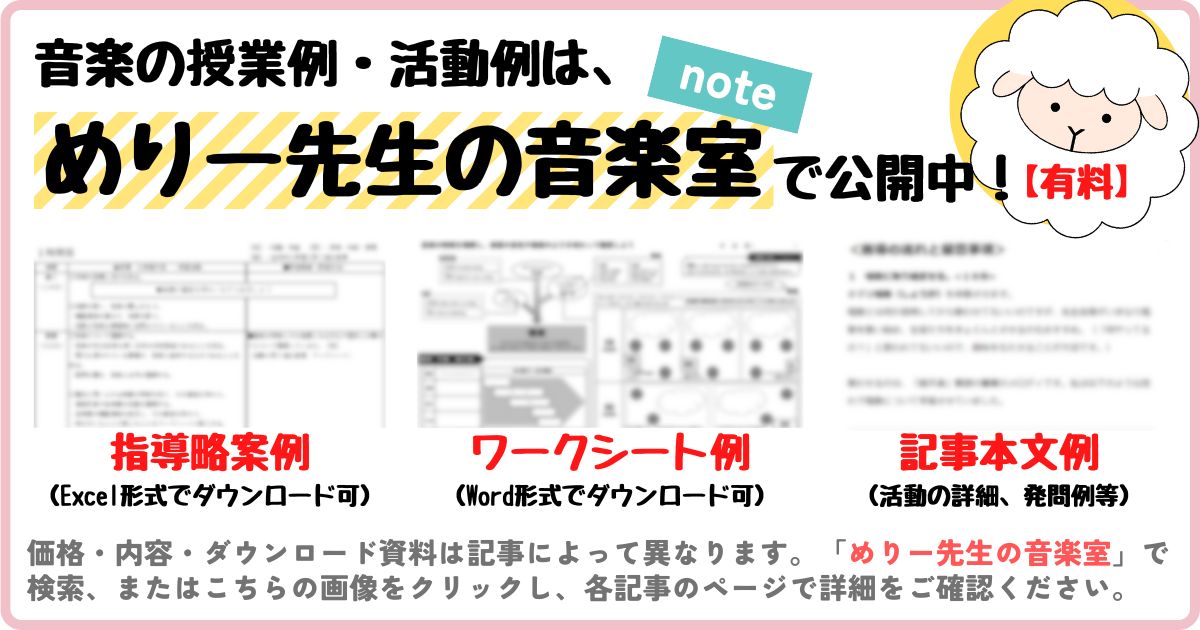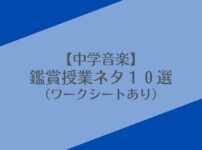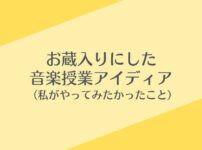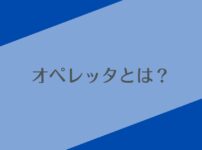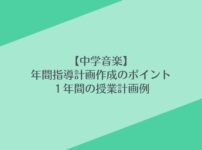この記事では、小学校の学習指導要領で示されている音楽を形づくっている要素を簡単に解説します。
音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。
-

【中学校】音楽を形づくっている要素とは?ざっくり解説
続きを見る
音楽を形づくっている要素とは?
小学校音楽科学習指導要領に示されている音楽を形づくっている要素は以下の通りです。
ア 音楽を特徴付けている要素
音色,リズム,速度,旋律,強弱,音の重なり,和音の響き,音階,調,拍,フレーズなど
イ 音楽の仕組み
反復,呼びかけとこたえ,変化,音楽の縦と横との関係など
【音楽編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 共通事項(1)より
音楽を特徴付けている要素
音色
音色は、声や楽器の表情、音の質、音の感じのことです。
笑顔や泣き顔といった表情があるように、音にも様々な表情があり、それにより聴き手が受ける印象も大きく異なります。
何か物を触った時の感覚と似ていて、「やさしい音色」「かたい音」「やわらかい音」などと表現します。
※声の場合は声色(こわいろ)とも言います。
リズム
リズムは、様々な長さの音符や休符の組み合わせのことです。
いろいろな長さの音や休止が組み合わさることによって生まれる拍の流れ、時間的な構造のことを指します。
曲を聴いて感じた印象から「細かいリズム」や「はねるようなリズム」などと表現します。
速度
速度は、演奏するスピードやその変化のことです。
音符1つあたりの時間の長さが大きく関わっていて、短ければ速く、長ければ遅く感じます。
その曲が速いか遅いかによって聴き手の受ける印象は大きく変わるので、曲の雰囲気を左右する大きな要素の一つです。
旋律
旋律は、音のつながり方のことです。
単なる音の高低変化ではなく、リズムを伴って連続的に連なることで生み出されるものを指しています。
音楽の授業では主旋律と副旋律を捉えたり、「ゆるやかな旋律」「音の上がり下がり」などと表現したりします。
強弱
強弱は、音量の大小とその変化のことです。
音が大きいか小さいかを相対的に捉えるものですが、単なる大小だけでなく、音色など他の要素と合わさった際の印象も含まれます。
例えば、小さい音でも弱弱しく頼りないと感じるものがあれば、逆に静けさの中の張り詰めた空気という印象を受けるものもあるといった具合です。
音の重なり
音の重なりは、複数の異なる音色や高さの音が同時に鳴り響くことです。
後述する和音も含まれます。
和音の響き
調のある音楽において、高さの異なる複数の音を同時に鳴らした際の響きのことです。
和音は、ルールに則って構成された、心地よく響く音の重なりのことを言います。
ゆえに、例えばピアノの鍵盤を両手でがしゃーんと適当に鳴り響かせた際の音は、正確には和音の響きには含まれません。
音階
音階は、音楽で用いられる基本的な音を高さの順に並べたもののことです。
西洋音楽では「ドレミファソラシ」のような7つの音で構成される音階が主流ですが、日本の民謡音階(5つの音)など、様々な音階が存在します。
調
調は、曲がどのような音階で構成されているかです。
大きく分けて長調と短調があり、何調かによって曲の雰囲気は大きく異なります。
拍
拍は、等間隔で刻まれるリズムの中の、ひとつひとつの時間のことです。
拍の流れが伸び縮みすると、曲の速度が遅くなったり速くなったりしたように感じられます。
フレーズ
フレーズは、自然に区切られるまとまりのことです。
短いフレーズ、長いフレーズなどと表現し、フレーズを生かして演奏することを「フレージング」と言います。
音楽の仕組み
反復
反復は、旋律やリズムが繰り返されることです。
呼びかけとこたえ
旋律やリズムが、問いかけと答えのように互いに呼応する仕組みのことです。
問いと答えが連続する場合もあれば、問いに対して答えが合間を置いて現れることもあります。
変化
変化は、曲の中で音楽の要素や仕組み、その関わり方が変わることです。
平たく言うと、旋律やリズムの形、速度、強弱、音色などが、曲の中で変わるということです。
音楽の縦と横との関係
音楽の縦を音の重なり方、横を時間的な流れをと考えた場合の関係性のことを言います。
縦は音の高さやリズムなどその一瞬における音楽の要素、横は音のつながり方や速度など音楽の流れの中で起こる変化を表しています。
まとめ
さて、この記事では小学校音楽科学習指導要領で示されている音楽を形づくっている要素それぞれの意味を簡単にご説明しました。
少しでもお役に立てていれば幸いです。

note「めりー先生の音楽室」へ
音楽の授業に役立ちそうなもの等を紹介しています!
↓ ↓ ↓


鑑賞授業
2025/11/14
映画「国宝」で話題!歌舞伎の演目分類と代表的な作品の紹介
元中学校音楽教員めりーです。 2025年に大ヒットした映画と言えば「国宝」ですよね。 映画を観て、歌舞伎の世界に興味をもったという方も多いのではないでしょうか。 ですが、いざ歌舞伎を実際に観てみようと思っても、作品がたくさんあるので、どれから観ればいいか分からないという方もいらっしゃると思います。 そこで、この記事では歌舞伎の演目分類と各カテゴリの代表的な作品をご紹介します。 目次歌舞伎の演目分類と代表的な作品時代物世話物松羽目物所作事義太夫狂言純歌舞伎新歌舞伎・新作歌舞伎まとめ 歌舞伎の演目分類と代表的 ...
ReadMore

鑑賞授業
2025/10/29
【中学音楽】鑑賞授業ネタ10選(ワークシートあり)
元中学校音楽教員めりーです。 もうすぐ新年度!ということで、note「めりー先生の音楽室」で公開中の記事の中から、特に人気の鑑賞授業例10記事を厳選してご紹介します。 いずれも中学校の鑑賞授業でマスト!と言っても過言ではない題材・教材なので、お役立ていただけたら幸いです。 目次中学音楽 鑑賞授業ネタ10選①「魔王」(中学1年)②「四季」より「春」(中学1年)③【雅楽】(中学1年)④「交響曲第5番ハ短調(運命)」(中学2年)⑤「フーガ ト短調」(中学2年)⑥「勧進帳」(中学2年)⑦【オペラ】(中学2年)⑧「 ...
ReadMore

授業ネタ
2025/10/28
お蔵入りにした音楽授業アイディア(私が教員時代にやってみたかったこと)
元中学校音楽教員めりーです。 私には、教員時代に思い付いたものの出来なかった授業や、教員を辞めてからふと思い付いた授業アイディアがいくつかあります。 今はもう教員を辞めてしまい実践は不可能ですが、このアイディアが先生方のお役に立てるのでは?と思い、ブログに書き留めることにしました。 学習指導要領や教科書、年間指導計画などは抜きにして、単純に「こんな音楽の授業をやってみたかった!」という内容ですので、参考にされる際には自己責任でお願いします。 目次私がやってみたかった授業アイディア・絵に合う音楽を選んでディ ...
ReadMore

授業の基本
2025/10/29
音楽授業の必要性について。元教員が考える「学校で音楽を学ぶ理由」
元中学校音楽教員めりーです。 時折耳にする「音楽の授業はいらない」という意見…元音楽教員としては少し複雑な気持ちになります。 というわけで、今回は永遠のテーマとも言える「なぜ学校で音楽を学ぶのか」について私なりの思いをまとめてみます。 一個人の意見ではありますが、音楽の先生方は、生徒から「どうして音楽の授業が必要なの?」と聞かれることもあると思うので、そんなときの受け答えのヒントとしていただければ幸いです。 目次将来役に立ててほしいから音楽の授業があるわけではない私が思う「学校で音楽を学ぶ理由」①様々な音 ...
ReadMore

鑑賞授業
2025/10/28
オペレッタとは?オペラとの違いや有名な曲も合わせて解説
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、オペレッタとは何かについて、オペラとの違いやそれぞれの代表曲と合わせて解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 目次オペラとは?オペレッタとは?オペレッタとオペラの違いは?オペレッタの有名な曲2選①「こうもり」序曲①「天国と地獄」序曲まとめ オペレッタについて説明する前に、まずはオペラについてです。 オペラとは? オペラは歌を中心に物語が進む歌劇のことです。 演劇と同じように、華やかな衣装に身を包んだ出演者が舞台上で ...
ReadMore

自習課題
2025/10/28
noteで公開中の自習プリント(中学音楽)を紹介します!
元中学校音楽教員めりーです。 急に音楽の授業が行えなくなった場合に役立つ自習プリント。 「いざという時のために用意しておきたいけど、忙しくて作る暇がない」という先生も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では、noteで公開中の授業資料から、すぐに使える音楽の自習プリントをご紹介します。 いずれも有料にはなりますが、一度購入していただければ長く使えるので、お役立ていただければ幸いです。 目次まずはこれ!音楽の自習プリント音楽記号・用語一覧プリント練習問題付き!楽典まとめプリントお楽しみ課題!クロスワ ...
ReadMore

授業の基本
2025/10/29
【中学音楽】年間指導計画作成のポイントと1年間の授業計画例
元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、年間指導計画作成のポイントと、1年間の授業計画(例)をご紹介します。 あくまで私が勤務していた頃の話にはなってしまいますが、参考にしていただければ幸いです。 目次年間指導計画作成のポイント①年間の授業時数を意識する②学校行事を確認する③評価の時期から逆算する1年間の授業計画例中学1年音楽 授業計画例中学2年音楽 授業計画例中学3年音楽 授業計画例(補足1)各題材で扱う教材について(補足2)実技テストについてまとめ 年間指導計画作成のポイント まずは、私が年間指導 ...
ReadMore

授業ネタ
2025/10/28
盛り上がる!音楽授業におすすめのゲーム「歌詞ビンゴ」
元中学校音楽教員めりーです。 音楽授業に取り入れると盛り上がりそうな、簡単なゲーム活動例を思い付いたので、ご紹介します。 その名も「歌詞ビンゴ」です。 授業のスキマ時間やお楽しみ会などに取り入れられるのでは?と思うので、参考にしていただければ幸いです。 目次歌詞ビンゴとは?歌詞ビンゴの進め方①ビンゴカードの作成・配布②曲を流してビンゴ大会!まとめ 歌詞ビンゴとは? 歌詞ビンゴは、その名の通り歌の歌詞を活用したビンゴゲームです。 所要時間は10分~30分で、準備もそんなに必要ないので、「少し時間が余りそうだ ...
ReadMore